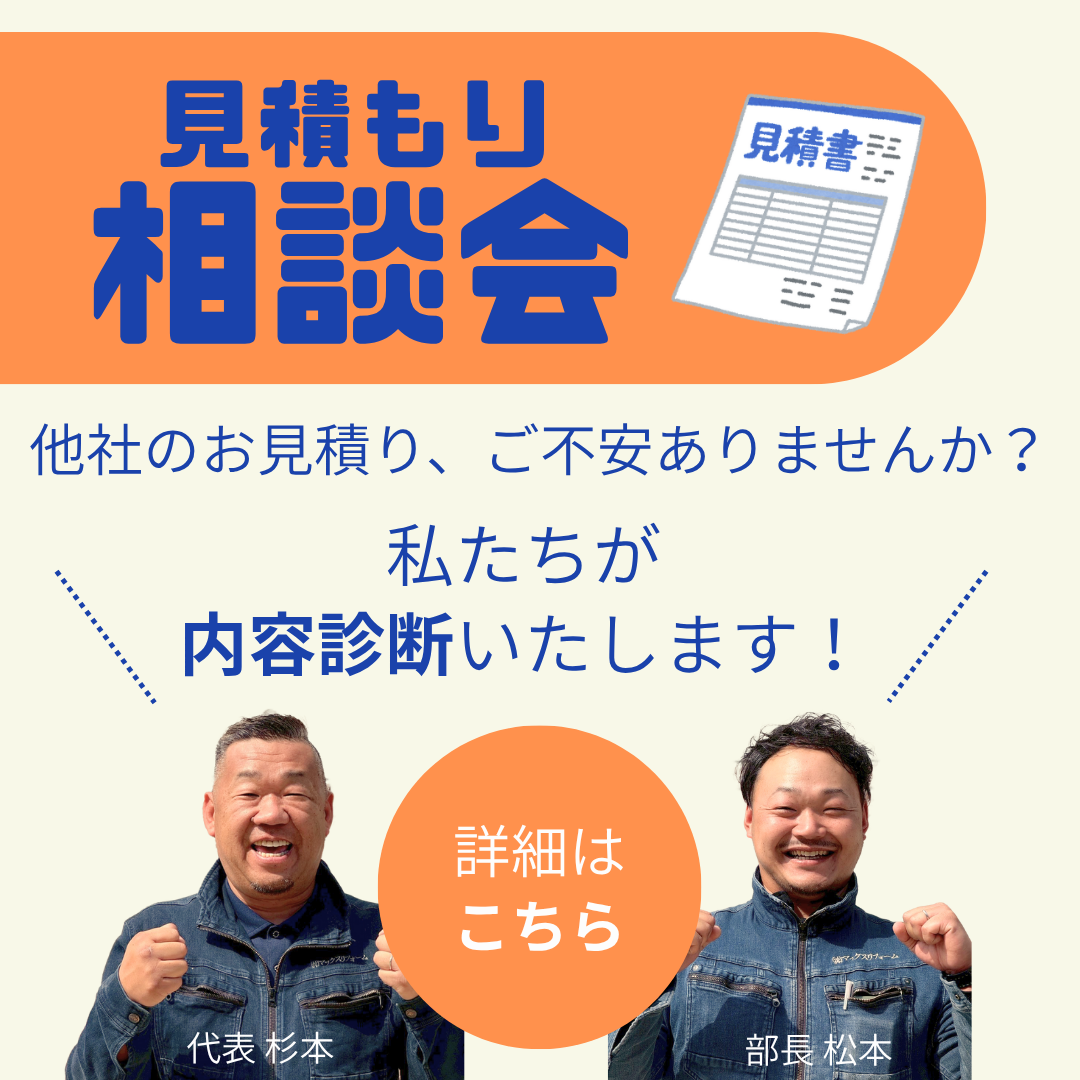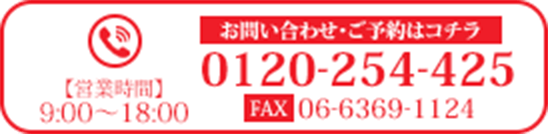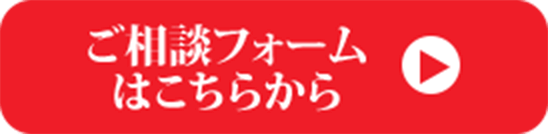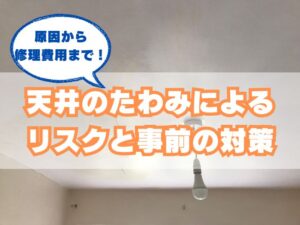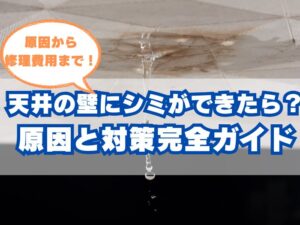茨木市のリフォーム助成金制度と屋根工事の活用術

老朽化した屋根の修繕やリフォーム工事を考えるとき、ネックになるのが「費用」の問題です。
ですが、茨木市では住宅に関するさまざまな補助制度が整っており、上手に活用すれば負担を減らして賢く工事を進めることが可能です。
このコラムでは、茨木市で利用できるリフォーム関連の補助金・助成制度についてご紹介しつつ、屋根工事との具体的な活用方法を解説します。
茨木市で使える住宅リフォーム関連の主な制度

【1】木造住宅耐震改修補助制度
- 対象者:昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者で、耐震診断を受けた方
- 対象工事:耐震改修工事(屋根の軽量化など)
- 助成額:最大100万円(工事費の8割以内)
- 適用されるケース:瓦屋根を軽量金属屋根へ変更し、建物全体の耐震性を高める場合など
- 適用されないケース:耐震診断を受けていない住宅、築年数が対象外の住宅
【2】長期優良住宅化リフォーム推進事業(国補助)
- 対象者:すべての住宅所有者(個人・法人)
- 対象工事:防水・断熱性能の向上、構造補強などの性能向上リフォーム
- 助成額:最大100万円(条件により加算あり)
- 適用されるケース:防水性や断熱性の向上を目的に屋根全体をリフォームする場合
- 適用されないケース:見た目の改修のみや部分的な補修のみでは対象外のことが多い
【3】多世代近居・同居支援補助制度
- 対象者:親世帯・子世帯が近居または同居を目的に住宅を改修する場合
- 対象工事:同居・近居のための住宅改修全般(屋根も含む)
- 助成額:最大20万円(条件による)
- 適用されるケース:同居を前提に屋根のリフォームや雨漏り防止を行う場合
- 適用されないケース:単身での改修、近居・同居を目的としない場合
【4】熱損失防止改修(固定資産税減額)
- 対象者:省エネ改修を行う個人住宅の所有者
- 対象工事:屋根、窓、壁の断熱工事等(一定要件を満たす必要あり)
- 助成額:翌年度の固定資産税が1/3減額(120㎡まで)
- 適用されるケース:断熱材を含む屋根改修工事を行い、全体で50万円以上の改修をした場合
- 適用されないケース:改修費用が規定以下、または断熱性能が一定基準に満たない場合
【5】重度身体障害者等住宅改造助成
- 対象者:身体障害者手帳1級または2級を持つ方のいる世帯
- 対象工事:バリアフリー改修に準ずる屋根・外部環境整備等(漏水防止など)
- 助成額:最大100万円(収入に応じて変動)
- 適用されるケース:漏水を防ぐための屋根の改修工事が、生活に支障を与える場合
- 適用されないケース:単なる美観目的のリフォームや補修箇所が障害に関連しない部分のみの場合
助成制度を活用した屋根工事の進め方

助成制度を上手に活用するには、計画的な進め方が重要です。以下の手順で進めるとスムーズに補助を受けながら工事を進行できます。
ステップ1:屋根の状態を把握する
まずは現在の屋根の状態を無料点検などでチェックしましょう。劣化状況や問題点を明確にすることで、適用可能な助成制度が見えてきます。
ステップ2:活用できる制度を調査・選定
屋根の状態を把握したうえで、どの助成制度に該当するかを市の窓口や専門業者と相談しながら確認します。
制度によっては事前診断や性能評価が必須になるため、早めの確認が肝心です。
ステップ3:助成対象に合わせた施工プランの作成
該当する助成制度の条件に合わせて、施工内容や資材選定を進めます。
たとえば、断熱性能の向上が目的なら省エネ基準に対応した建材を使用する必要があります。
ステップ4:見積書・申請書類を準備
必要書類(工事見積書、設計図、施工前写真、耐震診断結果など)を業者と連携して準備し、提出します。
提出先や様式などは制度によって異なるため、茨木市の公式HPや窓口で確認が必要です。
ステップ5:市の審査・内定後に着工
申請が受理されると審査に入り、補助金交付の内定が出ます。
交付決定前に着工すると補助金が受けられなくなるため、スケジュールには特に注意しましょう。
ステップ6:工事完了後の報告・実績提出
施工完了後は、施工後写真・領収書・完了報告書などを提出し、正式な補助金受給手続きを行います。
内容に不備があると支給が遅れるため、業者としっかり連携することが重要です。
茨木市で助成制度を利用する際の注意点

事前申請のタイミングに注意!
多くの助成制度では「工事前の申請」が義務付けられています。工事を先に始めてしまうと、補助金の対象外になるので要注意です。
書類の不備・遅れはNG
点検報告書や見積書、施工前後の写真、耐震診断結果など、求められる書類が多岐にわたります。
提出期限や書類の様式にも注意し、施工業者と連携して確実に準備しましょう。
対象要件の細かなチェックが必要
補助制度ごとに定められた「住宅の築年数」「所有者の条件」「工事内容の範囲」などをクリアしていないと、申請が通りません。
市のホームページで最新の要件を必ず確認しましょう。
年度ごとの予算枠がある
補助金には「年度予算」が設定されており、早期に受付終了となることも。
年度初め(4月以降)に動くのが理想です。迷っている場合でも早めに相談しておくとスムーズです。
対応業者の選定も成功のカギ
助成制度に精通した業者であれば、必要な書類や条件を的確に把握しており、トラブル回避につながります。
茨木市で実績のある専門業者に相談しましょう。
茨木市で助成金を利用した屋根工事を成功させるために
屋根リフォームを成功させるためには、単に助成金を利用するだけではなく、「信頼できる業者選び」と「適切なプランニング」が重要です。
茨木市の制度を活かしながら、満足のいく工事を実現するためのポイントを押さえておきましょう。
地元での実績がある業者を選ぶ
茨木市の住宅事情や助成金制度に詳しい業者は、補助金の申請手続きや書類作成にも慣れており、スムーズな進行が期待できます。
また、地元密着型の業者であれば、万が一のトラブル時にも迅速に対応してもらえるメリットがあります。
助成金に合った工事内容の提案をしてくれるか確認
例えば「耐震改修補助制度」を使いたい場合、ただ屋根材を変えるだけではなく、建物全体のバランスを見ながら耐震性を高める提案が必要です。
制度の条件に適合した具体的な施工内容を提案してくれる業者かどうかがカギとなります。
必ず事前に現地調査を実施しよう
現地調査を怠ると、施工中に予想外の劣化や構造上の問題が発見され、工期の遅れや追加費用の発生につながることも。
経験豊富な業者は、こうしたリスクも見越したうえで最適な提案をしてくれます。
見積もりの内容は細かくチェック
見積書には、使用する屋根材の種類、施工面積、工期、足場代、廃材処理費など、詳細な内訳が明記されているか確認しましょう。
助成金の申請にも必要な情報となるため、曖昧な見積書では後々トラブルの原因になります。
長期的なメンテナンスまで視野に入れる
屋根工事は一度施工すれば長く安心できる反面、将来的なメンテナンス費用を抑えるためにも、耐久性の高い素材や防水・断熱性のある仕様を選ぶことが重要です。
助成制度を活用して「今後もメンテナンスしやすい屋根」にするという視点も大切です。
スケジュール管理と制度の申請タイミングに注意
助成制度には、予算枠や受付期限が設けられている場合が多く、年度の前半(4月〜夏頃)に申請が集中します。
計画から申請、着工までのスケジュールを逆算し、タイミングを逃さないように注意しましょう。
助成金を利用した屋根工事でよくあるトラブル事例と防止策
屋根リフォームに助成金を使うのはとてもお得ですが、申請や工事の進行においてトラブルが発生することも。事前に知っておくことで、防止や早期対応につながります。
事例①:申請前に工事を始めてしまい、助成金が受けられなかった
トラブル内容:工事の緊急性から、申請前に着工してしまった結果、助成対象外となり全額自己負担に。
防止策:助成制度は“工事前の申請”が原則です。見積もりや設計書の準備が済んでから、必ず申請・内定を経て着工しましょう。
事例②:必要書類の不備で審査に時間がかかり、工期が遅延
トラブル内容:施工業者が作成した書類に不備があり、再提出となって着工が大幅に遅れてしまった。
防止策:制度に詳しい業者に依頼し、申請書類は事前に市役所や専門家にチェックしてもらうのが安心です。
事例③:対象工事と認められず助成金が出なかった
トラブル内容:「屋根塗装だけ」「雨漏り修理のみ」の軽微な改修が、性能向上に該当しないとして却下された。
防止策:対象工事の条件(耐震・断熱・防水などの性能向上)をきちんと確認し、制度に適合するプランを業者と一緒に立てましょう。
事例④:業者選びに失敗し、助成制度に対応してもらえなかった
トラブル内容:制度の内容を把握していない業者に依頼したため、書類準備に時間がかかり申請に間に合わなかった。
防止策:「茨木市での申請実績がある」「助成金制度に詳しい」と明記された業者を選ぶのが鉄則です。
事例⑤:申請は通ったが、工事後の実績報告が不十分で支給が遅延
トラブル内容:完了後の報告写真や領収書が足りず、追加提出を求められて支給が2ヶ月以上遅れた。
防止策:工事中から報告用写真を業者と共有・保管し、完了後の書類提出もすぐ対応できる体制にしておきましょう。
事例⑥:年度予算に達していて申請できなかった
トラブル内容:工事計画を立てていたが、申請時期が遅くすでに助成受付が終了していた。
防止策:助成金は“早い者勝ち”の側面もあります。4月〜6月にかけての申請を目指し、事前相談はお早めに!
茨木市で助成金を利用した屋根工事でよくある質問
Q1. 助成金と保険(火災保険・地震保険)は併用できますか?
A. 基本的には併用可能です。ただし、同じ損害や工事内容に対して重複して補填を受けることはできません。たとえば火災保険で補償される修理費用と助成金の対象が重なる場合、差額分のみが助成対象になるケースもあります。事前に業者や市に確認しましょう。
Q2. 自分で申請するのは難しい?業者に任せても大丈夫?
A. 書類準備や手続きには一定の知識と労力が必要ですが、多くのリフォーム業者が申請サポートを行っています。茨木市の制度に詳しい地元業者であれば、必要な資料の準備や窓口対応までしっかりフォローしてくれるので安心です。
Q3. 助成金が受けられなかった場合の支援制度はある?
A. 助成金対象外となっても、火災保険や地震保険、省エネ住宅ポイント、住宅ローン控除、固定資産税の減額制度などを活用できる場合があります。補助金にこだわらず、複数の制度を総合的に検討するのがおすすめです。
Q4. 助成金の申請から交付まではどのくらい時間がかかりますか?
A. 制度によって異なりますが、申請から審査・内定・交付決定まで1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。書類不備があるとさらに遅れる可能性もあるため、余裕をもって計画しましょう。
Q5. 助成金の申請前に工事を始めてしまったらどうなりますか?
A. 多くの制度では「着工前の申請・審査」が必須です。補助金の内定が出る前に工事を開始すると、原則として助成の対象外になります。申請タイミングには十分ご注意ください。
Q6. 屋根のどんな工事が助成金の対象になりますか?
A. 耐震性や断熱性、防水性など「住宅性能を向上させる工事」が対象になります。例として、瓦から軽量屋根材への変更、断熱材の追加、雨漏り対策などが該当します。見た目だけの改修や部分補修は対象外となる場合が多いです。
Q7. 助成金には所得制限や年齢制限がありますか?
A. 制度によって異なります。一部制度では、重度障害者の方や一定収入以下の世帯が優先されるケースがありますが、多くは所得や年齢を問わず利用可能です。制度の詳細は茨木市の公式情報をご確認ください。
Q8. どの制度が自分に合っているのかわからない場合は?
A. まずは屋根の点検を受け、劣化状況や目的(耐震・断熱・同居など)を明確にしましょう。その上で、市の住宅課や制度に詳しい業者に相談すれば、適した制度の提案が受けられます。
Q9. 助成制度には予算枠があると聞きましたが、どうすれば間に合いますか?
A. はい、年度ごとの予算があり、申請が多いと早期終了となることもあります。できるだけ4月〜6月ごろに計画を立てて動き始めるのがベストです。少しでも迷ったら早めに無料相談を利用しましょう。
Q10. 助成金を使った工事の保証やアフターサービスはありますか?
A. 助成金制度自体には保証はありませんが、信頼できる施工業者であれば、工事後の保証書発行や定期点検などのアフターサポートが用意されていることが多いです。契約前に保証内容も確認しておくと安心です。
まとめ
補助金制度は、しっかりと条件を確認すれば大きな味方になります。費用面の不安を解消しながら、住まいをより快適に、安全に保つ第一歩です。
まずは無料相談・現地調査から、気軽にご相談ください。
お問い合わせ
無料点検をご希望の方は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください!
- 電話番号:0120-254-425
- メールアドレス:info@maxreform.co.jp
- 公式LINE:LINEでお問い合わせ
- 予約カレンダー:こちらをクリック
- Zoom無料相談:予約はこちら
ご相談・お見積もりは無料です。茨木市での屋根リフォームをお考えの方は、ぜひ一度ご連絡ください!